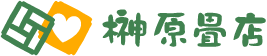畳干し|畳の湿気をリセットしてダニ・カビ予防を!畳干しメリットや方法、重たくて運べないときの裏技をご紹介します
こんにちは、榊原畳店です。
前回、シロアリのセルフチェックということで畳の外し方のお話をさせて頂きましたが、
せっかく畳を外したなら是非おすすめしたいのが
「畳干し」です。
畳を干して、畳の湿気をリセット!畳干しは畳を長持ちさせる効果があります
畳干しとは
畳を外して、屋外に干して、畳を乾燥させてあげることです。
昔は年に1回か2回、畳を干す習慣がありました。
昔はわら床ばかりでしたが、時代と共に木質チップを圧縮した建材ボードの畳床が出てきたので畳を干す習慣もすっかりなくなってしまいましたがわら床の畳のお宅ではまだ続けて下さる方がいると信じたいです✨
畳干しをする畳の種類
畳の中身が「わら床」の畳です。
わら床はお部屋の湿気を吸収したり、放出したりする調湿機能が高いです。
※木質チップを圧縮した建材ボードの畳はする必要はありませんが、畳の下の床板を乾かしたい場合は是非畳を外して乾かしてください。
畳干しをするのに良い時期
春「4/29畳の日付近」
寒い冬が終わり、コタツをやカーペット等で湿気を含んだ畳を、晴れた春の日に干して乾燥させましょう。
秋「9/24秋の畳の日付近」
9/24は「秋の畳の日」でもあり、「環境衛生週間」の始まりの日です。
冬の衣替えが始まる前に秋の大掃除です!夏のじめじめした湿気を含んだ畳を、秋晴れのカラッと晴れた日に畳を干して乾燥させてあげてください。
畳干しのメリット
畳が長持ちする
畳はお部屋の湿気を吸ったりはいたりする調湿機能があります。湿気を吸いすぎて飽和状態になってしまいます。畳干しで乾かしリセットしてあげることで畳も長持ちします。
ダニ・カビの原因を排除します
ダニやカビは湿気を好みます。畳を乾燥させることで寄せ付けない予防になります。
紫外線をあてて殺菌!
コロナ禍でも注目された紫外線の殺菌効果。畳に付着した菌を太陽の自然光(紫外線)でやっつけましょう。
床板も乾き長持ちする
床板も湿気を含むとカビの原因になり、傷んでしまいます。
畳を外し、風通しをよくして、床板も乾かしてあげてください。
昔は新聞紙を細長く破いたものや茶殻を床板にばらまいて、より湿気を取りやすくしていたそうです。
床板の異常に気付くことができる
シロアリの被害や床板の傷みを早期発見できるので早目の対処ができます。
畳干しの方法
①番号をつける

畳は1枚1枚位置が決まっています。
戻せなくなるといけないので、分かるように畳に番号をふりましょう。
②畳を外す
畳の外し方はコチラをご覧ください↓↓↓
③畳を干す

畳を裏向きにして、たてかけて干してください。
表面を太陽に向けてしまうとやけてしまう(退色を早めてしまう)ので気を付けてください。
日中4~5時間を目安に干し、
畳を戻して畳干し完了です!
畳干しをしたいけれど、畳が重くて外に運べないとき・・・
畳の中身がわら床の畳は25~30kg位重量があり、大変重たいです。
裏技★空き缶をかませる

そんなときは無理に干そうとせず、畳を少し持ち上げて、空き缶(できればスチール)をかませてください。
お部屋の窓を開けて風を通してあげましょう。たまに缶の場所をずらしてあげるとまんべんなく畳や床下を乾かすことができます。
畳屋を呼ぶ

畳干しをご希望の方はご相談ください。
お天気の良い日に朝お伺いして畳を干し、夕方にお部屋にお戻し致します
まとめ
最近では見かけない畳干しですが、ご年配のお客様は昔はやっていたよーとお話をしてくださいます。30代の女性でも実家がお寺で沢山畳があったそうで、子供の頃よく干してました!とお話を聞かせて下さいました。
畳を干してくださる方に共通している点は、畳が好きな方でした。
好きだから手入れをしてくれる、
手入れが習慣化していたから自然と愛着がわいてきた、
等きっかけは色々かもしれませんが、大好きな車を洗車するように、畳のお手入れにも目を向けてくださると嬉しいなぁと思います。
畳の湿気もリセットされて、長持ち、ダニ・カビ予防にもなり、良いことづくしです!

当店では畳替えの際ご希望のお客様に「畳干しサービス」をさせて頂いております。
お預かり日数を1日余分に頂き、畳をしっかりカラッと乾燥させて、
新しい畳表への取替え作業に入らせて頂きます。
是非ご利用ください。